|
|
|
浦和高校グリークラブは、現在、2年生20名、1年生18名、の計38名で活動している男声合唱の部活動です。日本では珍しい高校の男声合唱部の中でも、これだけの人数が集まっている学校は、多くはありません。男声合唱にしかない力強さの中にも柔らかさを感じられるような音楽を目指し日々頑張っています。
グリークラブとは
グリークラブの定義は、
・アカペラで三部編成以上の合唱団
・キリスト教系大学の合唱団
・キリスト教系宗教曲を中心に歌う合唱団
以上の3つのようですが、現在は単に男声合唱団をグリークラブと呼ぶのが一般的のようです。通常、パートは四声の場合、高音からトップ・テノール、セカンド・テノール、バリトン、バスからなります。
男声合唱の世界
現在男声合唱の世界は、残念ながら他の混声合唱や女声合唱ほど活発ではありません。曲のレパートリーやCD等の音源の種類、店頭に置いてある楽譜の数なども、混声や女声に比べて遥かに少ないという状況です。その理由としては、もともと男声合唱は変声期を過ぎた男子でないと難しいため、中学校で男声合唱を行い演奏者を育て増やすということはかなり困難であることや、公立高校の共学化により男子校の男声合唱部が潰れてしまうことなど、学生時代に男声合唱に触れる機会がなく、結果的にピラミッドの底辺を増やすことが非常に困難であることが主な理由の一つとして挙げられると思います。そんな男声合唱の世界に、浦和高校グリークラブが少しでも貢献出来れば幸いです。
部史
現在把握している公式な記録で浦和高校グリークラブの最古の参加記録は、1964(昭和39)年の第9回合唱祭への参加記録です。しかし、参加申し込みに遅れてプログラムには載らなかったとのことです。しかし当時のグリー在籍者によると、1963(昭和38)年頃には10名強の部員がおり、1964(昭和39)年に合唱部をグリークラブと改名する、グリーバッチの作成などを行う、コンクール出場を目指すなど活発に活動をしてたそうです。しかしその後、しばらくの間グリークラブの活動は低迷、詳しいことはよく分かっておりません。そして、1976(昭和51)年、浦和高校に松村健太郎先生が着任されると同時に、浦高グリーが本格的な活動を開始したとあります。当初は部員数わずかに6名で、練習も週に2,3回でしたが、あっという間に急成長を遂げます。それまで吹奏楽部と合同で開催していた定期演奏会を単独で行うようになったのは1978年、当時出演者は既に48人という大所帯でした。その後も70名を越える人数でのコンクール出場、2度の関東大会出場など、松村先生の指導により浦高グリーは素晴らしい基礎を築き上げました。
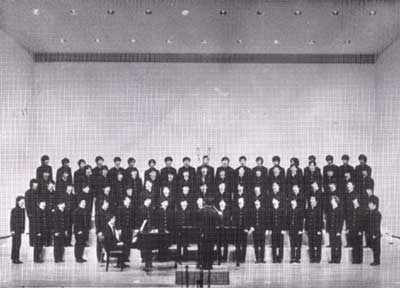
1983年に松村先生が異動されて大橋勝司先生が着任されると、また浦高グリーの新たな時代が始まります。「しっかりとした御自分の音楽理念をお持ちで」と紹介されている大橋先生の指導は熱心かつ大変厳しいものであったようで、様々な部分から窺い知る事ができます。部員数には恵まれなかった時代でしたが、男子校合同演奏会の開催や、定演では女子高との混声合唱の実現、また卒業生による作品の演奏や大橋先生ご自身による作曲や著名な宗教曲の男声版編曲の演奏など、浦高グリーがいよいよ活発に様々なことを取り組み始めるのも、この時代の特徴です。浦高グリーの歴史の半分を占めるこの期間が、浦高グリーを安定させたと言えるでしょう。

2000年、大橋先生の後に着任されたのが田中洋安先生です。浦高が2校目という若さでありながら、田中先生の指導で浦高グリーは更に成長を遂げ、関東大会に頻繁に出場できるまでになります。また、田中先生の「生徒の自主性を尊重するスタイル」はグリーの活動の幅をさらに広げ、第24回定演以降は毎年全て生徒で作り上げるポピュラーステージが登場するなど、現在のグリーの一番の特徴である「生徒による自主運営」を確立させました。

2005年、田中先生が県庁に異動され、福岡高校から小野瀬照夫先生が浦高グリーの新顧問となられました。福岡高校の前は川越女子高校音楽部の顧問もされていた小野瀬先生は、合唱のベテランで、その親しみやすいお人柄と相俟って部内の支持は絶大です。そして、第30期は、関東大会にて10年前と同じ、金賞をいただきました。そして2008年、第33期で、夢にまで見た浦和高校初の全国大会出場を果たし、銀賞を受賞しました。その後も浦高グリーは第36期、第37期と2年連続で県大会において県知事賞を受賞、5年連続の関東大会出場となった第40期は7年ぶり2度目の全国大会出場など活躍を続けております。今後も浦高グリーをよろしくお願い致します。
最終更新日:平成27年10月24日
|
|
|
|